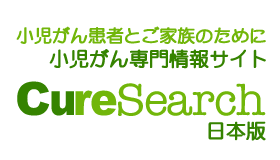数ヶ月後から数年後に
父親と母親が同じように悲しむことは、あまり無いようです。そのため、パートナー以外の人に自分の気持ちを打ち明けることがあります。亡くなった患児の話題を持ち出すと相手を傷つけるかもしれない、と配慮するからです。また、パートナーのどちらかがより強く悲しんでいる場合、両者の間に葛藤が生まれることもあります。
また、「患児が亡くなって1年も経てば、気持ちが落ち着くだろう」と思う親もいるかもしれません。少しずつ日常を取り戻すかもしれませんが、つらい思い出が消え去るわけではありません。時間とともに患児が目の前にいないことを実感するので、「2年目の方がつらい」という家族もいます。
あるいは、周囲のサポートが減ることで、そう感じるのかもしれません。家族の苦しみがどれだけ続くか、どう対応すればよいか分からないからです。親も「周りの人はもう触れたくないのではないか」と感じます。
確かに、2年目になれば、親は前向きになるべきだという感じが周囲にはあります。その人たちは「親は、残されたきょうだいや親自身の未来に、もっと目を向けて欲しい」と思うでしょう。
そのような親には、親族や友人と集まり、亡くなった患児のことを気兼ねなく話せるように、追悼の会や、時にはイベントを行うこともよい方法でしょう。患児のことを話したり記憶をたどることで、「患児が忘れられてしまうのではないか」という不安の軽減になります。
深い悲しみや苦しみを和らげるために、心理療法士や心療内科医などの専門家の力を借りることもよい方法です。病院によっては、院内に親のための支援グループを設けている場合があります。また、病院外でも、がんでこどもをなくした親や、病種や年齢を限定しない遺族グループなどもあります。まずは参加してみて、合わなければ他のグループに参加するなど、時間をかけて自分に合う方法を探してみましょう。
悲しみや苦しみがあるとき、不安やうつ病の薬は一時的に役に立つかもしれません。しかし、依存し過ぎてはいけません。必ず専門医に相談し、服用を決めた場合は必ず定期的なチェックを受けましょう。薬だけ処方されるということは稀で、カウンセリングとの併用療法が用いられます。薬が必要なくなった時には、専門家は安全に服用をやめるサポートもします。
患児のきょうだいも、親同様に悲しみを感じています。親の顔、しぐさ、涙に、患児を思い出します。彼らにも、専門家の助けや、同じような経験を持つ同年代のこどもたちからのサポートが必要かもしれません。稀に、こどもにも投薬が必要な場合もあります。しかし、一番のサポートはともだちである場合がほとんどです。彼らに専門のカウンセリングを受けるように促しても、初めは「要らない」という答えが返ってくるでしょう。思春期になれば、カウンセラーに会ったり、支援グループに入ることを望む場合もあります。患児への思いをオープンにして、患児の名前を何度も口にすることで、思い出が心の中に生き続けるのです。
また、「生きていたら、必ずこうしたはず」とか、「絶対にこれはしなかったはず」など、患児を理想化することは、残されたきょうだいに対して不公平ですし、亡くなった患児のことを知っている人にとっては非現実的なことです。きょうだい各自の個性と長所を大事にするよう心がけていないと、彼らは理不尽な比較をされたままで生きて行くことになります。
かかりつけの小児科医は、きょうだいの様子を公正に判断してくれます。きょうだいがどう対処しているか不安な場合には、医師に専門的な意見を求め、親子のためのカウンセラーを紹介してもらうとよいでしょう。
複雑性悲嘆(抑うつ状態と心的外傷性反応)
大切な人を失うという悲しみは誰にでも起こり、避けて通ることはできません。わが子に先立たれてしまった親は深い悲しみ、怒り、罪悪感を持つこともあります。患児が亡くなるまでのことを思いだし、自分自身や周りの人を責めるかもしれません。
患児の死後数ヶ月の間にうつ病の症状がみられる人もいます。亡くなった患児の声が聴こえる幻聴や、人ごみの中で顔を見たりする幻覚などを経験することがあります。これは多くの場合、こどもに戻ってきて欲しいという強い望みや、諦めきれない気持ちなどの激しい感情から起こると考えられています。このような反応は、わが子を失ったことへの普通の反応です。これに対しては、治療ではなく、慰めや状況の説明などが必要です。
しかし、その症状が長引き(6ヶ月以上)、しかも次第に悪化する場合は「複雑性悲嘆」と呼び、通常の悲しみと区別します。死を受け入れられなかったり、いつまでもその人のことが頭から離れず日常生活が混乱したり、人間関係が崩れたりします。この場合、うつ病や心的外傷などの疾患が合併していることも多く、精神科的な治療の対象となります。
ここでの特徴的な症状は、亡くなった患児のことが頭から離れない、患児が亡くなったことを否定する、生き返ることを想像する、絶望的な孤独感と無力感と辛さ、死んでしまいたいと思う、などです。
複雑性悲嘆を発症するリスクは、その死がどの程度の心的外傷(トラウマ)として受け止められたかに左右されます。例えば、患児を「自宅に連れて帰る」「緩和ケアのみを受けさせる」とはっきり決断した親は、複雑性悲嘆を発症するケースが少ないということが研究で分かってきました。また、積極的な治療を続け、末期に延命措置の回避を決めた親も、発症するケースが少ないようです。この精神疾患は、心の準備がない状態で、予期しない形の死に遭遇した後に起こる可能性が高いのです。
葬儀に出るかどうか、亡くなった患児の話をするか、サポートグループに参加するか、薬を服用するかどうかということは、それぞれが「悲しみにどう対処するか」を明確にしたうえで選択することです。家族や親族を亡くしてから通常の状態に戻るまで、長い時間がかかる人もいます。専門家は、以前は「治癒には約1年」、現在では「2年でも十分ではないかもしれない」と言います。それ以上かかる人もいますが、「昨日よりも良い日になる」と前向きに希望を持つことができた人は、「悲しみに対処している」と考えられます。
反対に、前向きな行動が停止したり、人生が生きるに値しないと思ったり、悲しみが日ごとに増す場合には、複雑性悲嘆であることが考えられます。
複雑性悲嘆の治療は、通常、抗うつ薬あるいは抗不安薬の投与と心理療法を併用します。心理療法では、なぜ罪悪感や自責の念が消えないのかを理解できるように、親がその経験を追体験するように導きます。また、悲しむだけではなく、亡くなった患児を裏切るような気持ちにならずに他の活動を楽しむことを考えるよう勧められます。また、パートナーや残されたきょうだい、他の家族がどのように向き合っているかを考えることも勧められます。深い悲しみにある自分自身や周囲の人のためにも、良い方法を見つけましょう。
日本語版更新:2020年5月